
このような状況は子育てを体験した多くの人が覚えがあると思いますが、「うちの子は、いつも怒ってばっかりで・・・」と嘆いている人は少なくありません。
子供のころは性格だけでなく、成長過程によっても怒りっぽくなることがあります。まずは、ご自身の子供のころを思い出してみてください。子供も不快な思いをしたくて怒っているわけではありません。
なぜ怒りっぽくなるのか、その原因や対処法について一緒に考えてみようと思います。
子供はどう表現すればいいかわからないから怒っている
まず、怒りという感情を心理学の観点で見てみることにします。心理学で、怒りは「感情の蓋」とよく言われるのですが、何らかの感情に蓋をするため、その感情を隠すために怒っているとされます。
「もどかしい」「恥ずかしい」「話したくない」などという時に怒っている人をよく見かけると思いませんか?これが感情に蓋をしている状態なのです。
蓋をし隠すことで嫌な感情を認めなくてもいいですし、そこから逃げることもできるからです。
子供の場合は、「わかってほしい」「助けてほしい」という表現方法がわからないから、自分や状況に対して怒りやすくなっている側面があります。
なので子供が突然怒り出したときは、何か言いたいことがあるんだと思ってあげてください。「怒る前に、言いたいことを言ってみてごらん」といった言葉をかけることで、子供も分からないながらも安心して話し始めることができると思います。
環境が変わることで怒りが誘発されることも
最初に子供が怒りっぽくなるのは2~7歳前後と言われていて、2~3歳はイヤイヤ期と言われ、自我の芽生えによって親への反発から反抗的な態度をとってしまって怒りっぽく見えるようになります。
4~5歳では幼稚園や保育園への入園、6~7歳は小学校への入学などの変化が怒りっぽさの原因になっていることがあります。集団行動が始まって他人と比べられる機会が増えることによってストレスを感じたり、思い通りにならない事を不快に感じたりして、怒りっぽくなることが多くなります。
運動会などの行事や、テストなどで周りの大人に優劣を決められたり、他の子供たちといろいろ比較されることで劣等感をもってしまう子供もいます。
そして、家庭の外でたまったストレスが親に対して爆発し、自分の子供はいつも怒ってばっかりというふうに見えてしまうという結果になります。
このような状況は、環境の変化に慣れてくれば、怒りやすい状態はそのうち消えていくのが自然の流れです。
両親や親族の性格も影響している
「子は親の背中を見て育つ」という言葉をご存じだと思いますが、親が感情の起伏が激しかったり、神経質だったりすると、当然のことながら子供も些細なことに敏感に反応してストレスをためて怒りやすくなってしまう傾向があります。
その反対に、両親が広い心で子供に接していると、些細なことにこだわらずに楽観的に何でも受け入れられるように育つことが多いのです。もし子供が怒りっぽいと感じるようでしたら、ご自身の接し方やふだんの生活を見直してみる必要もあるのではないでしょうか。
かんしゃくの強さにも影響される
怒りっぽい性格は、2歳頃に起きるかんしゃくの強さにも影響されるという事がわかっているようです。かんしゃくが強かった子供が、そのまま怒りっぽい性格になる傾向があって、例えば、お絵かきが上手にできなかったり、ブランコの順番がなかなか来ない時にかんしゃくを起こす場合があります。
満たされない自分の欲求を怒りで表現することを覚えてしまうとされます。かんしゃくを起こしている時は、怒りをしずめるためにその怒りの理由を聞いてあげたり、その場を離れて気を紛らわせたりするといった適切な対処が必要となります。
子供が怒っている時は背景に何があるのかを考えて、話を聞いてあげることが大切です。頭ごなしに叱ったりせずに、しっかりと「何が原因で怒っているのか」を一緒に考えてあげるようにしてください。
GIQでは、検査の結果をもとにどのようにして子どもと接していくのかが、とても重要だと考えています。
安心の国内検査でお子様の才能を開花【GIQ子ども能力遺伝子検査】
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)





















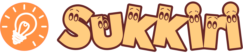
この記事へのコメントはありません。